納豆をつくってみました。
自家製納豆にチャレンジしました。
結論からいうと、自家製発酵食品の中では上級編になりますね。
納豆になることはなりますが、すこし難しい印象です。
あまった大豆でつくってみました。
納豆をつくってみました。
味噌用に買った大豆が微妙にあまったので、前からやりたかった納豆つくりにチャレンジです。
ネットでリサーチする限り、それほどハードルが高い感じでもありません。
まずは、鍋で100gほどの大豆を4時間煮ました。

納豆というと、藁の中にいる納豆菌で発酵させるイメージです。
実際に、その方法で納豆をつくった知り合いもいます。
しかし、ネットによると、それでは雑菌が入るなど、すこしリスキーのようですね。
一番完璧なのは、納豆菌を使う方法です。
ところが、その納豆菌、Amazonでもってしてもなかなかのお値段なのでした。
そこで、今回は次策の、市販の納豆から菌を抽出する方法でトライしました。
大豆の煮汁に大さじ一杯の納豆を入れてカマカマすると、納豆菌液ができるようです。
あとは、これを煮えた大豆に振りかけて、40℃ほどの環境で18時間ほど放置ですね。
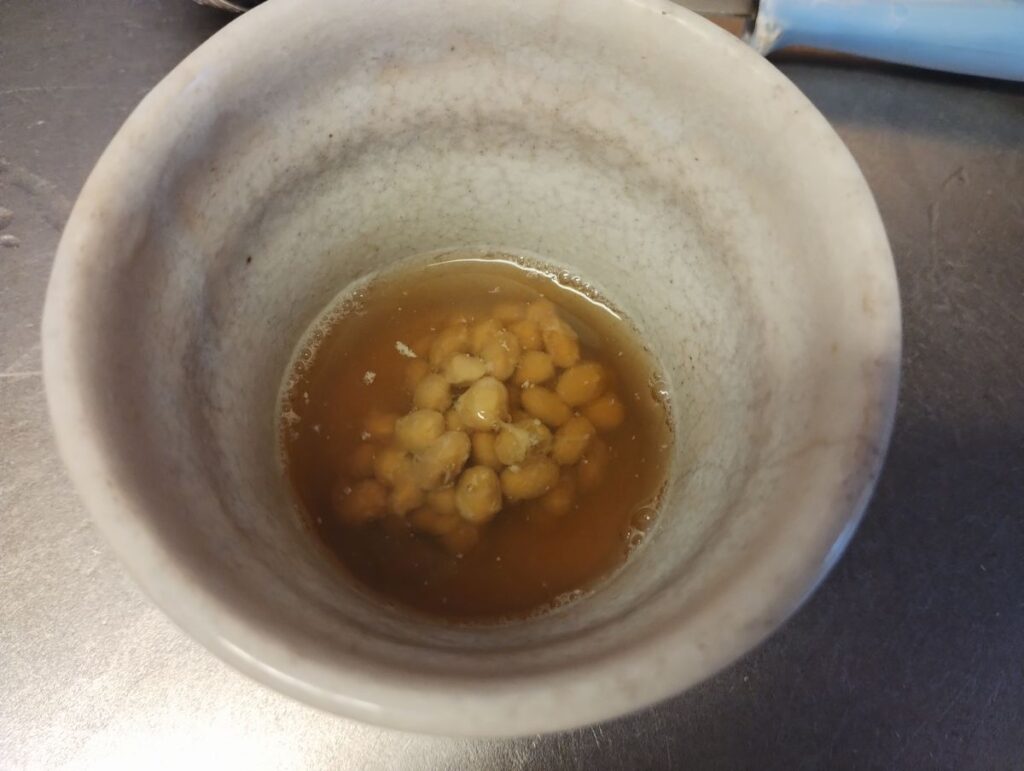
問題は、その40℃の環境をいかにしてつくるかですね。
炊飯器ではうまくいきませんでした。
40℃の環境は、ヨーグルトメーカーがあれば完璧らしいです。
しかし、ヨーグルトメーカーは持ち合わせがないので、代わりに炊飯器を使ってみました。
保温状態の炊飯器は、温度計で確認すると60℃ぐらいです。
すこし高めですが、納豆菌は120℃でも死なないようですので、なんとかなるでしょう。

18時間後、ただの固い豆ができあがりました。

糸はまったく引かず、本当に納豆の風味がするだけの、ただの固い大豆です。

これはこれで、お酒のつまみにはなりましたが、でも、結論的には失敗ですね。
その後、帰省したときに、母親にこの話をしました。
そうしたトコロ、母親の実家では、かつて納豆を自作していたとのコトです。
それで、ポイントは発酵時の温度のようですね。
これが高すぎても低すぎても、糸を引く納豆にはならないとのコトでした。
はかせ鍋にホッカイロでリベンジです。
ということで、母親からのアドバイスをもとに、圧力鍋て煮た250gの大豆でリベンジです。
今度は、はかせ鍋を使って発酵させてみました。
この鍋は、鍋の温度を数時間にわたってキープすることができます。
これでカレーをつくると最高なのですが、この保温機能は納豆つくりにも使えそうですね。

圧力鍋て煮た大豆をはかせ鍋に移し、そこに市販の納豆から抽出した納豆菌を振りかけます。
はかせ鍋の底面にホッカイロを貼って、40℃前後の発酵環境を実現しました。

翌日、大豆の表面が白くなって糸を引いていました。

味も、まごうことなき納豆です。
大粒で、食べ応え十分の納豆ができました。

おもしろいのは、その味ですね。
納豆菌を抽出した市販の納豆とは、まったく別の味になりました。
なるほど、納豆の味は豆で決まるようですね。
それで、この自作納豆、これはこれで素朴でおいしいのですが。
しかし、市販されている納豆の、あの洗練された味には程遠い感じです。
どうしたら、あの市販品の味が実現できるのか、納豆つくりの道はまだまだ続きそうです。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません