草刈機を修理しました。
今回は、オートバイではなくて草刈機の話題です。
2stエンジンの草刈機を修理しました。
草刈機のような農耕機は、機械的にはオートバイの従妹のようなモノだと思います。
修理自体にも、どこかオートバイに通じるモノを感じました。
実家の草刈機が吹け上がらなくなりました。
カブとガンマの整備が一段落ついて、残すは900SSのキャブ修理です。
しかし、その前に実家の草刈機を直さなくてはいけません。
こちらも、8月に草刈りしたときから、スロットル全開で失速する状態です。
9月のお彼岸に草刈りをする予定ですので、それまでに何とかしなくてはいけません。

不調の理由については、おおよそのアタリはついています。
たぶんキャブの目詰まりというコトで、バラシて清掃すれば直るでしょう。
ということで、まずはエアクリボックスもとい、エアクリカバーを外します。

草刈機らしく、エアクリにはたくさんの砂埃が付着していました。
これは、あとからエアーで吹いておきます。

次に、キャブと共締めになっているチョークユニットを外します。

チョークの構造はとてもシンプルで、閉じたときはこんな感じですね。
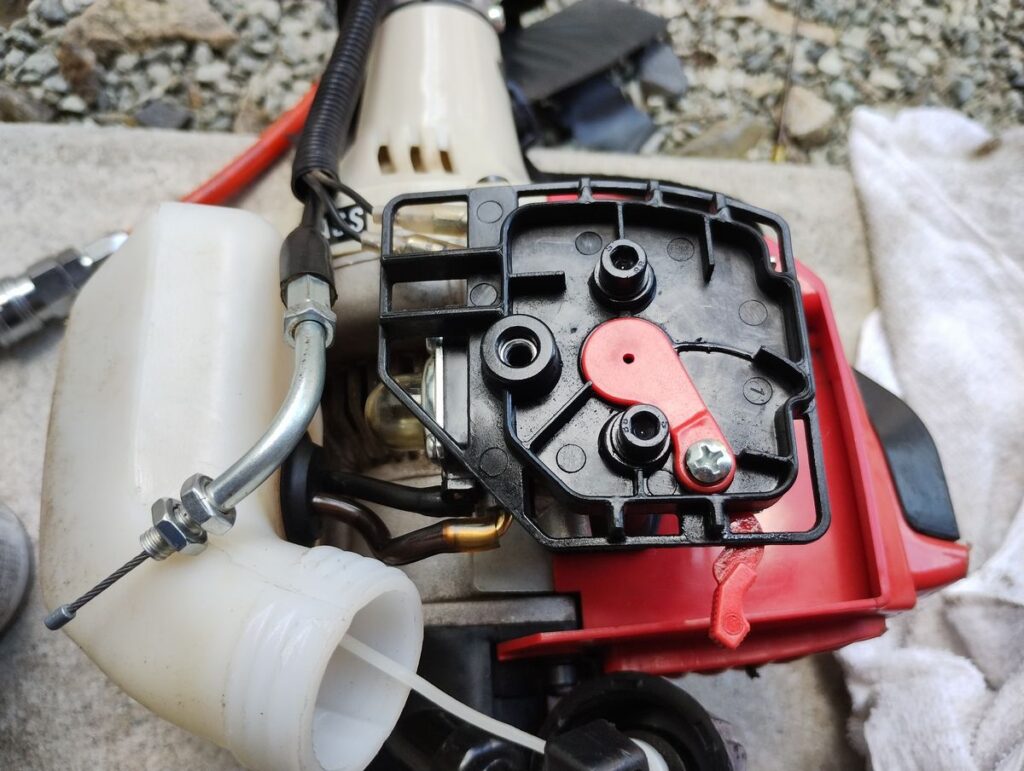
チョークユニットを外せば、今回の主役、キャブレターとご対面ですね。

あとは、スロットルワイヤーと燃料ホースを外してキャブを取り外します。
このあたりは、カブのキャブ以上に楽勝ですね。
草刈機のキャブはダイヤフラム式です。
取り外したキャブを、Bikeのキャブでいうトコロのスライドピストン側からバラします。

草刈機の場合は、スライドピストンではなくスロットルバルブですけどね。

これがクルッと90度回転することで、スロットル全開になります。
オートバイのキャブレターと違って、JNの位置はスロット開度に関わらず、常に一定ですね。
Walbroのキャブレター、草刈機やチェーンソーのキャブは、だいたいがここのモノのようです。

スライドピストン側の次は、フロー室側の分解です。

とはいえ、ダイヤフラム式の草刈機キャブには、フロー室という概念はありません。
Bikeのキャブのフロー室に相当する部分には、ダイヤフラムというゴム板があります。
それが、エンジンの脈動で上下に動いて、ベンチュリ―管に燃料を供給します。
草刈機は天地返しすることもあるので、オーバーフローしないこのタイプ一択になるようですね。
ということで、まずは始動に必須のプライマリーポンプを外します。

噂のダイヤフラムとご対面ですね。

ダイヤフラムを破かないように慎重に外しました。

今回は、フロートバルブもチェックしました。
慎重にネジを外して、フロートバルブのピンを抜きます。

フロートバルブも大丈夫そうでした。

しかし、こんな複雑なトコロに混合ガソリンを入れたら、目詰まりするのも自明ですね。
あらためて、草刈機には定期的なメンテナンスが必要だと思いました。
キャブの清掃で無事に復活しました。
バラバラにしたキャブレターは、しばしキャブクリーナー漬けにします。
汚れが分解される間に、草刈刃を取り付ける部分のギアボックスをグリスアップしました。

オートバイのメンテナンスに例えると、チェーンの清掃とグリスアップですね。

グリスは、ギアボックス横のグリス穴から投入します。

ギアボックスを回すワイヤーにもグリスを塗っておきました。
ここは、オートバイのメーターギアと同じですね。

ギアボックスのメンテが終わったら、キャブの修理に戻ります。
穴という穴をエアーで吹いて、元通りに組み立てました。

あとは、本体に組み込んで完了ですね。

最後に試運転がてら、庭の芝の際を刈ってみました。
草刈機で芝を刈ると、笑えるぐらいにメチャクチャ刈れます。
刈りすぎてしまわないように、慎重に芝に刃をあてました。

そして結論、草刈機も完調になりました。
スロットルを全開にしても失速することなく、ウルトラスムーズに吹け上がります。
これで、キャブ整備第二弾も無事に完遂ですね。
それではいよいよラスボスの、900SSキャブ整備に心置きなく取りかかりたいと思います。




